最近、生成AIを使っていると「Gen ID」という言葉を目にすることが増えましたよね。でも、「Gen IDって何?」「ChatGPTやGeminiでも使えるの?」と疑問に思っている方も多いはず。
実は、Gen IDは生成AIをもっと便利に使うための重要な機能なんです。一度理解すれば、AIとのやり取りがグッと効率的になります。
この記事では、Gen IDの基本的な意味から具体的な使い方、身近な生成AIでの対応状況まで、わかりやすく解説していきます!
Gen IDとは?まずは基本を押さえよう
Gen ID(ジェネレーションID)とは、生成AIが作り出したコンテンツ一つひとつに割り振られる「識別番号」のことです。
簡単に言えば、AIが生成した画像や文章に付けられる「背番号」や「管理番号」のようなものと考えてください。
たとえば、AIに「猫の絵を描いて」とお願いして3枚の絵が生成されたとします。このとき、それぞれの絵には異なるGen IDが付けられ、「1枚目はGen ID: 12345」「2枚目はGen ID: 12346」といった形で管理されるんです。
Gen IDがあると何ができる?
- 気に入った作品を後から簡単に見つけられる
- 同じ設定で別のバージョンを作り直せる
- 生成したコンテンツの履歴を追跡できる
- 他の人と作品を共有する際に特定しやすくなる
つまり、Gen IDは「このAIが作った作品はこれです」と証明する大切な目印になるわけですね。
なぜGen IDが重要なのか?3つの理由
ここで少し反対側から考えてみましょう。「Gen IDなんて別にいらないんじゃない?」と思う方もいるかもしれません。
でも実際に使ってみると、Gen IDがないと困る場面がたくさんあるんです。理由を一つずつ見ていきましょう。
①作品の管理がラクになる
生成AIを使っていると、たくさんの画像や文章が生まれます。Gen IDがなければ、「あのとき作った良い感じの画像、どこ行った?」と延々と探すことになります。
でもGen IDがあれば、番号で検索すれば一発。図書館の本に管理番号が付いているのと同じ仕組みで、時間の節約になるんです。
②再現性が高まる
「この画像の雰囲気で、もう1枚作りたいな」と思ったとき、Gen IDがなければ同じプロンプト(指示文)を入力しても、まったく違う結果になることがあります。
でもGen IDがあれば、同じ設定やスタイルを正確に再現できます。偶然できた良い作品を、意図的にもう一度作れるようになるんです。
③トラブル対応がスムーズに
もし生成されたコンテンツに問題があったり、権利関係の確認が必要になったりしたとき、Gen IDがないと「いつ、どんな条件で作ったか」が曖昧になります。
Gen IDがあれば、作品の出所が明確になるので、特に商用利用する場合に安心できるんです。
具体的にどうやって使う?Gen IDの活用方法
では、実際にGen IDをどう使うのか、具体的な手順を見ていきましょう。
思考の流れとしては「確認→保存→活用」という3ステップで考えると理解しやすいです。
使い方①:生成した作品からGen IDを確認する
多くの生成AIでは、作品の詳細情報欄やメタデータ(作品に付随する情報)にGen IDが記載されています。
確認方法の例
- 画像を右クリックして「プロパティ」や「詳細情報」を表示
- AI画面の作品の下に表示される番号をメモ
- 生成履歴のページでIDをチェック
- 画像ファイル名に含まれている場合もある
使い方②:Gen IDを使って作品を検索・呼び出す
Gen IDをコピーしておけば、後から検索バーに入力するだけで、その作品をピンポイントで探し出せます。
例:「Gen ID: 98765を表示して」とAIに指示
これで、数百枚の中から一瞬で目的の画像が見つかります!
使い方③:Gen IDを共有する
他の人と作品を共有したいときは、画像ファイルそのものではなく、Gen IDを伝える方法もあります。
相手が同じAIサービスを使っていれば、IDを入力するだけで同じ作品を見られるんです。データ容量も節約できて一石二鳥ですね。
使い方④:バリエーション作成に活用
「このGen IDの作品をベースに、色違いを3パターン作って」といった指示も可能。元の作品の雰囲気を保ちながら、新しいバージョンが作れます。
身近な生成AIでGen IDは使えるの?
ここが一番気になるポイントですよね。「普段使っているChatGPTやGeminiでGen IDは使えるの?」という疑問にズバリお答えします。
結論から言うと、身近な生成AIのほとんどでは、Gen ID機能は使えません。
ここから一つずつ、各AIの対応状況を見ていきましょう。思考プロセスとしては「そのAIが個別の生成物をIDで管理しているか」がポイントになります。
ChatGPT:Gen IDは使えない
OpenAIが提供するChatGPTでは、残念ながらGen ID機能は実装されていません。
画像生成機能(DALL-E)を使っても、生成された画像一つひとつにGen IDが表示されることはないんです。会話全体にはIDが付きますが、個別の生成物を追跡する仕組みではありません。
Gemini:Gen IDは使えない
GoogleのGeminiも同様に、Gen ID機能には対応していません。
画像生成を含め、生成されたコンテンツに個別のGen IDが割り振られる仕組みはないため、特定の作品を後から番号で探すことはできないんです。
Copilot:Gen IDは使えない
MicrosoftのCopilotでも、Gen ID機能は利用できません。
画像生成時に内部的には何らかのIDが付いている可能性はありますが、ユーザー側から確認したり利用したりすることはできない状態です。
Qwen:Gen IDは使えない
中国のAlibaba Cloudが開発したQwenも、現時点ではGen ID機能を提供していません。
テキスト生成が中心のAIですが、生成物に対する明確なID管理システムは確認されていないんです。
Claude:Gen IDは使えない
AnthropicのClaudeも、厳密な意味でのGen ID機能はありません。
ただし、Artifact(作品)機能を使った場合は、各Artifactに識別子が付与されるため、近い機能は利用できます。でもこれは「Gen ID」とは異なる仕組みです。
じゃあ、Gen IDはどこで使えるの?
Gen ID機能をしっかり使いたいなら、画像生成に特化した専門的な生成AIを選ぶ必要があります。
※2025年10月時点の情報です
MidjourneyはJob IDという形で各画像に番号を付与し、Discord上で簡単に管理できます。Leonardo AIもGeneration IDが画面上に明確に表示され、作品の追跡や再生成がスムーズに行えます。
つまり、Gen IDを本格的に活用したいなら、MidjourneyかLeonardo AIを使うのが最適解ということになります。
注意:身近なAIでの代替方法
ChatGPTやGeminiでGen IDが使えないからといって、作品管理ができないわけではありません。
代替方法
- 会話URLを保存しておく
- 生成した画像をフォルダ分けして管理する
- プロンプト(指示文)をメモしておく
Gen IDほど便利ではありませんが、これらの方法でもある程度の作品管理は可能です。ただし、完全な再現性や他者との共有の面では、やはりGen ID対応のAIには及びません。
まとめ:Gen IDを使うなら専門AIを選ぼう
Gen IDは、生成AIで作った作品を管理・追跡・再現するための「背番号」です。
この記事のポイント
- Gen IDは生成コンテンツに付けられる識別番号
- 作品管理、再現性向上、トラブル対応に役立つ
- ChatGPT、Gemini、Copilot、Qwen、ClaudeではGen IDは使えない
- Gen IDを使いたいならMidjourneyかLeonardo AIがおすすめ
- 身近なAIでは会話URLやファイル管理で代替可能
- 本格的なクリエイティブ作業にはGen ID対応AIが有利
普段使いのAIと、クリエイティブ作業用のAIを使い分けるのが賢い選択です。
「ちょっとした質問や会話」にはChatGPTやGeminiを使い、「作品を作り込んで管理したい」ときにはMidjourneyやLeonardo AIを使う——こんな使い分けがベストですよ。
Gen IDの機能を理解して、自分の目的に合った生成AIを選んでくださいね!

ではでは、参考までに。
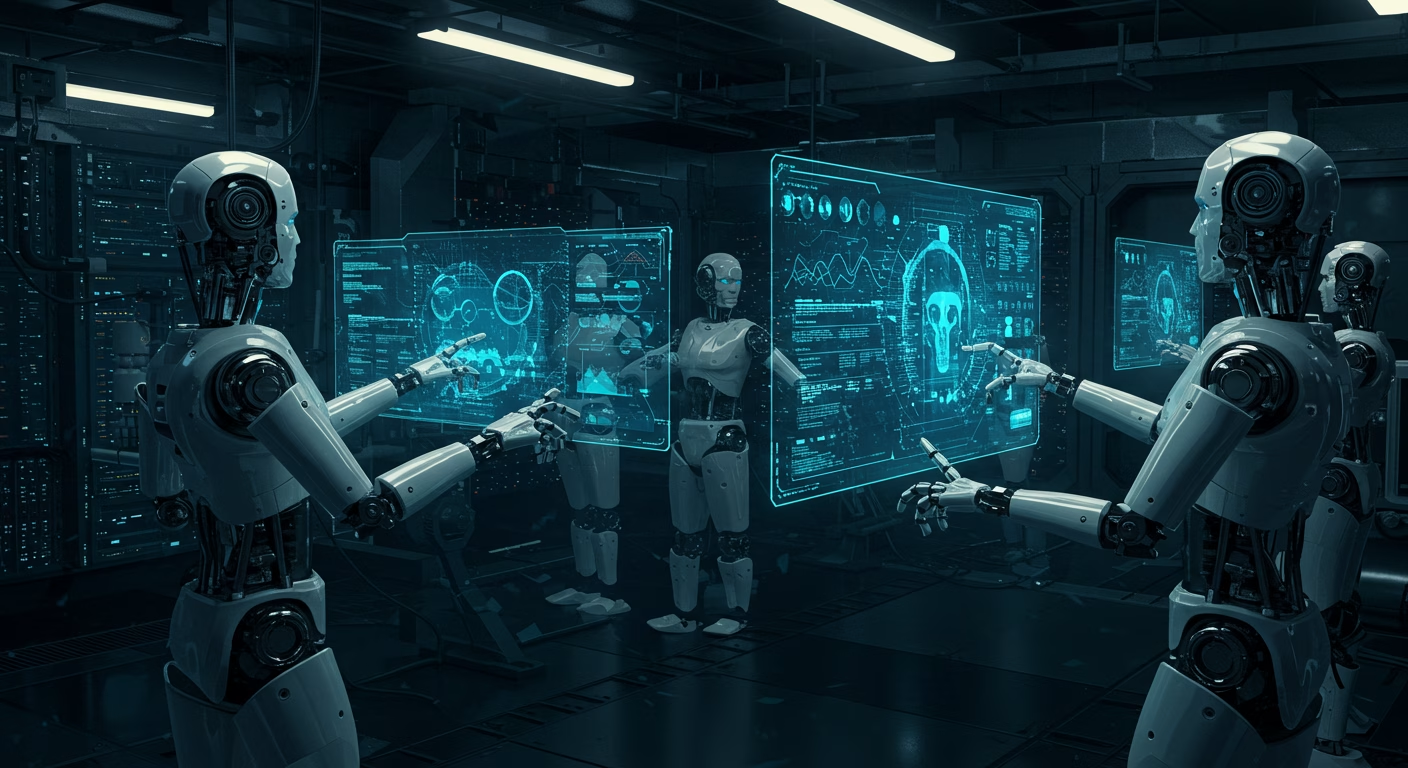
コメント